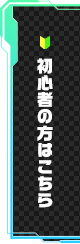2018.11.25 【 2024.06.16 update 】
残されたもの
南アフリカ某所、なんの変哲もない資材倉庫の地下にそれはある。
知る人ぞ知る秘密の研究所を訪ねたのは、出るべきところがしっかり出ている豊満な身体つきの女性。対象的に控えめで華奢な白衣の女性が、その金髪碧眼の女性を出迎えた。
「ようこそ! 来てくれてありがとう!」
「セーラと私の仲じゃないですか。固いこと言いっこナシです。なんなら九頭竜の学生時代みたいに〝シシシシマ〟って呼んでくれても構いませんよ?」
「あれ言いにくいから、もう言わない」
「そんな! 寂しいこと言わないでください」
「七尾こそ〝デース〟しゃべり、やめちゃってるじゃん」
「日本語にもすっかり慣れましたから」
ふたりの名は倉敷世羅と獅子島七尾。
久方ぶりの再会に話が弾む。
「学生時代かあ……。最近、あいつらなにしてるか知ってる?」
「レイアとスグルなら正義の味方をしてますよ。ふたり乗りの変形する車だかで荒野を駆け回ってます」
「相変わらずね」
「武力がすべての時代ですから、弱者には頼られ、強者には疎まれているみたいですね。さて――」
世間話がひと段落ついたところで、七尾ははるばる遠い地へ呼び出された理由を聞き出すことにした。
「用件は、黒崎博士関連ですか?」
「うん……」
七尾は一瞬、世羅の表情が陰ったのを見逃さなかった。
一方、世羅もまた、七尾に以前ほどの覇気が見られないことに気付いていた。
「もうね、聞いてよ! そのみかにいがさあ!」
暗い雰囲気を嫌う世羅が、わざとらしく明るい声を振り絞る。
「私が考案した、鉱石に擬似生命を与える技術について、七尾にも話したことがあったと思うけど。あれに関するレポートをドヤ顔で見せたのよ。そしたら、至極適切な改善アドバイスを赤ペンで記入されて、米国巨大企業を抱えるハイドラ財団をバックに取り付けてくれて、こんな立派な研究所まで用意してくれちゃったりして、至れり尽くせり。机上の空論だった無機生物ギガンティックが、あっという間に実用レベル。みかにいを見返すために始めた研究が、気が付けば、みかにい無くしては実現できないアレやソレの塊ってわけ。不条理極まりないわ!」
世羅は不機嫌と照れ隠しのないまぜな不思議な表情で、書類の積まれた研究机を叩いた。
「まあまあ……。確かハイドラ財団はブレイバーの開発にも関わってるって話ですよね。主力商品の性能を高めるための競争相手として、セーラの生み出す鉱石生物ギガンティックは、うってつけということでしょうか」
「みかにいもそんな感じで出資を提案したみたい」
「私の母国の企業なのでよく知ってるのですが、セーラが嫌うタイプじゃありませんか、ハイドラ財団は?」
「うん。態度でかいからね。でも、資金面は最大のネックだったし、背に腹は代えられなくて」
「だったら日本の三大財閥に頼るという選択肢も」
「ダメダメ。百目鬼は真っ黒すぎてなにを代償に求められるか分かったもんじゃないし、上柚木も百目鬼の親戚筋だからお察し。マトモなのは蝶ヶ崎くらいだけど、あそこはミソスの資金援助に手一杯なはず。ああ、ミソスってのは――」
「ソーリィ」
話が脱線してきたため、七尾は世羅の説明を遮った。
「そろそろ本題を聞かせてくれますか。……おそらく話し辛いことなのだとは思いますが」
図星を突かれた世羅は俯いた。
苦しげに、息を吐き出すように、ぽつりぽつりと語り始める。
「みかにいが、おかしくなっちゃった……」
「フゥム。確かに業界筋では、アーサーほか九大英雄を放逐している黒崎博士を、歴史的戦犯と見る向きが多いですね。彼らが各地で争いを繰り広げ、ほかのブレイバーを扇動して回るせいで、世界はひどく混乱していますから。……もしかして、すべて黒崎博士が故意に仕組んだことなのですか?」
「分かんない。そんなことより、みかにいはブレイバーのはるか上を行く強さを持つ《最凶生物》を創り出すって言ってて……」
「ブレイバーのはるか上ですか。想像もつきません。……それが?」
「誰にも制御不能なんだって。みかにいにも。なのに、半年後には完成した《最凶生物》を量産して世界を滅ぼすって、私に……」
突拍子のない話に七尾は絶句した。
「きっと妹の復活がうまくいかなくて、どうかしちゃったんだ……」
神門は事故死した妹を復活させるため、最先端の科学と百目鬼の錬金術を組み合わせ、ブレイバーの技術を生み出した。
しかし、その技術を応用して本懐を遂げたという話は聞こえて来ない。
「みかにいが本気を出せば世界を滅ぼす生物くらい創れると思う。でも、どうして私に言うんだろう。子供の頃からずっとみかにいに憧れて、遠すぎる背中を追いかけて、夢を手伝いたいって言い続けてきたけど、ほとんど相手にされなかったのに……。いまさら、こんなのってない!」
「……私の想像ですが」
涙を滲ませる世羅に七尾は優しく語りかけた。
「黒崎博士もセーラのことが大切なんです。そんな恐ろしい生物を生み出すに至った経緯は知りませんが、だからこそどうしようもない事情があって、セーラに助けを求めたんじゃないですか?」
「……!!」
頼りにしてくれているのかもしれない。
そうであれば嬉しいと心の片隅で考えていたことを七尾にも指摘された世羅が、涙をこらえるように唇を噛む。
「やっぱり、そう……なのかな。私の勘違いじゃない……のかな?」
七尾は力強く頷いた。
「だったら、私がみかにいを止める。半年以内に九大英雄に匹敵するくらいのギガンティックを創らなきゃ。話を聞いてくれてありがとう、七尾! まだ時間あるよね? しばらく泊まっていってよ! いっぱいおしゃべりしたい!」
「もちろん構いませんが、倉敷博士に提案があります」
「どしたの。急に改まっちゃって?」
「研究助手は要りませんか」
七尾は世羅の下につき、ギガンティックの知識を一から学んだ。中学生の年齢で大学へ進学したような頭脳を誇るだけあり、あっという間に遺伝子工学の数々の理論を修得してゆく。
機械に触れられないという体質的なハンデを背負う世羅にとって、心を許せる優秀な助手の存在は、心身ともに助けとなった。
それから数ヶ月が経ち――
最強のギガンティック軍団が神門のブレイバー研究所を取り囲んでいた。
大小様々な鉱石生物が居並ぶ中でも、ひときわ大きく輝く、まるでドラゴンのような姿の個体が10。超重量をものともせず、空を舞うものもあった。
「黒崎博士を止めるには、最終調整が終わるまでに《最凶生物》を沈黙させなくてはなりません」
「うん。ギガンティックとブレイバーの全面戦争」
「あのコたちに名前は付けないんですか?」
「検体1号とか2号のままでいいよ。この戦いで死なせちゃうかもしれないのに、可愛げのある名前なんて無理」
「では、せめて九大英雄に相当するシリーズ名をつけませんか?」
「それなら考えた。暁十天ってどうかな」
「夜が明けて、天に羽ばたく10の翼……ですか。いいですね。胸に刻み込みます」
七尾は目を瞑り、数ヶ月間の思い出とともに、その名を反芻する。
そして、決意の瞳で世羅に告げた。
「では、手筈通り私が先に潜入します。パパやママほどじゃありませんが、磨いた忍者スキルが役立つ時です!」
「気をつけて!」
「心配ご無用デース!」
先行してブレイバー研究所に忍び込んだ七尾の役目は、研究所のシステムと電源系をシャットダウンすることだった。
数分後、研究所の明かりが一斉に消えた。どうやら成し遂げたらしい。
あとは混乱のるつぼに陥った研究所へ世羅が攻め込むのみである。
「私たちもがんばろう。……みかにい、もうすぐ行くからね」
世羅は暁十天に突撃を命じた。
あちこちから火の手が上がっている。もの言わぬ鉱石塊に戻った仲間たちや、応戦するも力尽き横たわるブレイバーたちを乗り越え、世羅が駆け抜ける。目指すは神門の研究室。だが、行く手を阻むモノがあった。
圧倒的な火力ですべてを焼き払い、なぎ倒す暁十天のパワーをもってしても、ソレは身動ぎしない。調整中と目されるにも関わらず、たかが2メートル少々の人型兵器《最凶生物》には、なにひとつ通用しない。動きの鈍さだけが唯一の救いだった。
――敵わない。遭遇してからわずか10秒で世羅は察した。
「みかにい! いないの!?」
呼びかけに返事はない。
目的を果たせず、とてつもない敗北感を味わわされた世羅は倒壊する研究所から脱出すると、七尾に連絡を入れた。
『無事ですか、セーラ?』
「無事だけど、ごめん。ダメだった。七尾も撤退して」
『私は目の前の《最凶生物》を停止させます』
「……え? あいつと戦ってるの!? どこにいるの!?」
質問に七尾は答えなかった。代わりに聞かされた言葉に、世羅の背筋が凍りつく。
『たったの数ヶ月でしたが、とても充実していました』
「なにそれ……。どうしてそんなこと言うの!?」
『いまここで私が決断しなければ、おそらく二度と、コイツを封印できません』
「しなくていいよ! 無理することない! やめて!」
『知っていますか、セーラ。私が子供の頃からずっと夢見て来たロボット社会は、膨大な電力を消費します。電力をつくるには資源が必要です。高度な演算を行うコンピューターも必要です。核戦争で多くを失い、荒れ果てたこの世界では、もう無理なんです……。私は進むべき道を見失っていました。そんな時にセーラから手紙をもらったんです』
世羅は再会した直後の七尾が精彩さを欠いていたことを思い出した。
あれは夢を諦めた顔だったのだ。
『死んだも同然だった私を、セーラは受け入れてくれました』
「当たり前じゃん親友なんだから! いまだってこれからだって、私には七尾が必要なの! また一緒に研究しようよ! あんなヤツなんかに絶対負けないギガンティックを、ふたりでつくろう!」
『アハハハ……。アリガト、アンド、ソーリィ。……ウゥ。ココはチョット寒すぎデースね……』
「こんなの嫌だよ! 帰って来て、シシシシマ!!」
『親愛なるセーラ、黒崎博士を見つけて、幸せに――』
それが最後の言葉となり、大爆発が起きた。
すべてが終わった後、世羅は崩れ落ちた研究所を再訪した。
ほどなくして地下へ至る階段を見つけると、火災から逃れていた区画を発見。その最奥、重く閉ざされた金属製の扉には七尾の筆跡で〝Don't open!〟の文字が乱雑に刻まれていた。
扉の向こう側に七尾がいる。あれから《最凶生物》と遭遇していないのが、なによりの証拠だった。おそらくこの中は時間が止まっている。すべてが氷漬けとなり……。
生命力の権化たる《最凶生物》ならいざ知らず、そんな生物と一緒に隔離され、冷凍庫のような場所で人間が生存できる可能性はゼロに等しい。いますぐ開け放ちたい衝動を必死にこらえ、世羅はその場を離れた。
世羅は激しく後悔していた。自分の問題に七尾を巻き込み、死なせてしまったことを。
世羅は激しく絶望していた。神門の期待に応えられなかったことを。
いつの日か《最凶生物》が扉を破って出て来るかもしれないのに、対応策も思いつかない。
自分への怒りは、いつしか、姿を現さない神門への怒りへ転嫁された。
生気を失い、ふらふらと地上へ出た世羅の眼前に、巨大な黒いドーム状の物体が鎮座している。
なぜだか直感的に、それは過去世界へ至るゲートのような気がした。
誰がなんのために設置したのか、いつの間にできたのか、危険はないのかなど、検証すべきことは山程あったが、もはやどうでも良かった。
「……ブレイバーなんて……創られなければ良かった……過去の黒崎神門を殺せば……二度と悲劇は生まれない……」
低い声で独り言を呟く彼女に付き従う10の影。
「一緒に来てくれるの? だったら、名前をつけてあげないとね」
暁十天の一匹の首筋を撫でながら、世羅は無感情に告げた。
「あなたはジェリーマ・アイカブ。罪と罰って意味」
殺意をまとわせた世羅と暁十天は、後に〝ブラックポイント〟と呼ばれるようになるゲートの向こうへ姿を消した。
これは、彼女が現代を生きる神門と邂逅し、心を救われる少し前の物語。