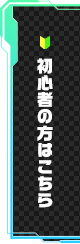2024.09.23 【 2024.11.04 update 】
どんなことも厭わない
信頼と愛憎の結末――青の世界黎明期の物語。信頼と愛憎の結末――青の世界黎明期の物語。

Illust. ちゃきん
01 side. HONOME
若くして財閥総帥となった蝶ヶ崎ほのめは、かつてライバル視していた黒崎神門から召喚を受けた。
財閥の本社ビル、ミスティカルサイトの受付嬢となった倉敷世羅も同伴している。いきなり呼び付けてきた相手が相手。私服に白衣を羽織って身構えた。
「なんだろね。すっごく叱られたあの日以来、すっごくギクシャクしてたから、すっごくドキドキする……」
「どうせロクでもない用件ですの」
機械科学が驚異的な発展を遂げつつある現在。
触れた機械を片っ端から壊してしまう世羅は、極めて肩身の狭い思いをしていた。大小の企業から近隣店舗に至るまで、出入禁止を言い渡されるなど日常茶飯事。類例の無い【機構破壊】の異能を解明せんと、誘拐未遂に巻き込まれた経験も数知れず。
同様に【組成破壊】の異能を隠し持つほのめは、目の届く範囲に世羅を保護した。
ほのめが趣味で続けている研究を、機械に接触しない範囲で手伝ってもらう場合もある。世羅自身は独自の研究を辞めてしまったが、天才肌の発想と頭の回転の速さは、大人となっても健在だからだ。
「例えば、そうですわね……。斜陽の蝶ヶ崎財閥をハイドラ財団へ吸収合併させる仲介役を請けたとか」
「悪く考え過ぎだよ。なんだかんだ言って、最後はいつも味方してくれるのが、みかにいじゃん」
「だといいのですが。近頃はさりげないアドバイスもさっぱりありませんのよ? ……いえ。それは私の至らなさが問題でしたわ。忘れてくださいまし」
「あほのめはいつも忙しいもんね」
「総帥様に向かって、あほのめ言うな! 時間さえあれば、私だって……」
幻獣を創出する夢を、現実に変えられるだろうか?
いまや遺伝子工学は神門ばかりか、誰からも関心を抱かれない学問となった。まるで〝そちら側へ傾かせない抑止力が働いている〟ようにさえ感じる。
専攻がズレてしまい、一番になれる機会とライバルを同時に失ったのがスランプの始まり。父や弟は謎の死を遂げた。傾き掛けた財閥を建て直す責務も重くのしかかる。研究に割ける時間的余裕が無いのは紛れもない事実である、が……。
やがて、ふたりは待ち合わせ場所のオープンカフェにたどり着いた。
「久し振り、みかにい! ……えっと。あのこと、怒ってない?」
「心配するな。〝水に流す〟と言っただろう」
「ほんと!? 良かったああああーーーー!!」
「相変わらず元気だな、世羅。あほのめも息災でなにより」
「総帥様に向かって、あほのめ言うな! アンタたちは私の扱いが軽過ぎですの!」
タイミング良く、エスプレッソとチップス、ココアとカステラがテーブルに届けられた。
給仕ロボに触りたくなる衝動を抑え、世羅がテーブルにつく。直後、カステラは消えて無くなった。
「……ごっくん。アラサーの私が〝みかにい〟ってのもないね」
「その単語はアラフォーの私に効くから、控えてくださいますの?」
遅れてほのめも席についた。
初秋の日差しを遮る屋根の下、三人は三角形を描くように対面する。彼らの馴れ初めから実に二十年の月日が流れていた。皆、年相応に成長し、あるいは老けている。人間なのだから当然の摂理である。
「黒崎さん? 神門さん? どう呼べばいいのかな? やっぱし神門かな?」
「いままで通りで構わん。関係性が変わるわけでもあるまい」
「うぐっ。私としては変えたいんだけど……。ま、いいや。とにかく、会えて嬉しい!」
「遺伝子工学に見切りを付けたアンタから呼び出しなんて、どういう風の吹き回しですの?」
懐疑的なほのめに、神門はこともなげに告げる。
自信に満ちあふれ、何度も煮え湯を飲まされてきた、憎たらしくも懐かしい表情で。
「おまえたちの〝脳〟を借りたい」
「おあいにくさま。電子工学に応用出来る知恵なんて、さほど持ち合わせていませんの」
「勘違いするな。浅知恵になど期待するものか。頭脳ではなく〝脳〟が欲しいと言ったんだ」
「……どういうこと?」
神門を信じ切っている世羅は、きょとんとした表情で首を傾げる。
天真爛漫な性格は、齢や苦労を重ねても、ほとんど変化がないように思われた。
「俺の研究目的が亡き妹の復活にあることは、薄々勘付いているだろう?」
「ええ。まあ」
「春日ちゃん復活のためなら―― 力を貸すよ」
「待ちなさいの、世羅。話は最後まで聞くべきですわ」
遺伝子工学を専攻していた当時の神門は、強靭な肉体の研究に没頭していた。
完璧な器に英傑の〝魂〟を宿らせ、無敵の兵士を創造する構想もあったという。
後半は裏ルートから極秘裏に仕入れた情報に過ぎない。だが、完成した技術を交通事故で喪った妹の復活に流用しようと考えていたならば、当時の尋常ならざる熱意に説明もつく。
しかしながら、計画は破綻した。残されたものは、クローン製造技術の初歩段階。
「百目鬼の協力を取り付けられなかったんですのね?」
「腐っても財界トップのひとり。察しが良いな」
原因は上層部の交渉ミス。神門の支援者であるロイガー・ダイナミクスが百目鬼財団と決裂した。
安倍晴明の再来と名高い百目鬼一族の当主は、環境破壊から目を背けながら躍進する機械科学を真っ向否定するNPO、リンドヴルム協会に囲い込まれている。英傑の〝魂〟を現世に喚び降ろす術は完全に封じられた。
「ならば発想を変えるまで」
「ロボットでも開発するつもりですの?」
「機械の身体にそこそこのAIを搭載するだけならば容易い。だが、そんなカラクリメカモドキを【春日】と呼ぶなど、鳥肌が立つ。俺は【春日】を創ってみせる」
神門はしばしば実現困難な発想を打ち出す。
不可能な妄想と思われても、あらゆる常識を覆し、最終的に達成してしまう。
その天才的頭脳と判断・実行力を前に、努力家の秀才であるほのめは、何度も敗北感を味合わされた。
だからこそ―― 続く彼の言葉は許せなかった。
「だが、サンプルとするべき【春日】は死んだ。俺の記憶だけを頼りに、ゼロから完璧な【春日】を創造するなど、いくらなんでも不可能だ」
「数々の逆境に打ち克ってきたアンタが、いまさら〝不可能〟と口にするんですの? 弱音を吐くなんて、青天の霹靂ですわね? 空はこんなにも晴れていますのに!」
「最期を看取れなかった。親が離婚して別居となったせいだ。俺が把握していない身体的特徴や精神的成長は、いくらでもあっただろう。希望のよすがの記憶さえ、日に日に薄れてゆく有様。……ならばこそッ!!」
神門は決意表明とばかりに、拳を握り締めた。
「記憶を集めねばならんのだッ!!」
「私たちは春日ちゃんをほとんど知りませんの。アンタに聞いた範囲がせいぜい」
「断片的な【春日】の記憶をかき集めたとて、完全なる【春日】の構築には到底至るまい。ゆえに、俺が欲するのは【春日】をまったく知らんヤツらの記憶だ。【すべての記憶】から【春日以外の記憶】を取り除けば、それは【春日】と断じても差し支えあるまい?」
耳を疑った。
ほのめの背筋を冷や汗が伝う。
「まさか……。全人類の記憶を集めるつもりですの? それこそ不可能ですの!」
「可能だ。時間さえ掛ければな。だが、人間の寿命は短い。生命の炎が先に尽きるだろう。ならば俺の〝脳〟をデータ化してAIに落とし込めばいい」
「理解の範疇を超えてますわ。そんな愚かな私に、アンタはなにを求めますの?」
「俺はおまえたちの才能を買っている。世羅の適応力。ほのめの根性。俺には遠く及ばんが、明晰な頭脳もな。なにひとつ成せないまま老いて失わせるには、あまりに惜しい」
「相変わらず歯に衣着せぬ物言いですわね……」
神門の傲慢な語り口調はいつも通り。慣れたもの。
……にも関わらず、薄ら寒さを感じる。いつも以上に感情を読み取れない。もとい、血の通った感情が汲み取れない。代わりに、要求される内容だけは想像がついてしまった。
世羅も同様なのだろう。怯えきり、すっかり言葉を失っている。
「初手として、おまえたちの〝脳〟をデータ化する」
「…………」
「次手として、速やかに俺の〝脳〟をデータ化しろ。世羅とほのめのデュアルコアなら、俺に匹敵する演算処理スペックになるはずだ。すでにハードウェアの準備は目処がついた。あとはソフトウェアのみ。俺が信頼するのはおまえたちだけだ。ほかの輩は誰ひとり信用ならん。三人で全人類を掌握しよう。そして【春日】を創ろうじゃないか」
「ふざけんな!!」
感じた恐怖は吹き飛んだ。妹ひとりのために、あまりにも身勝手な発想だった。提案された計画には、極めて重要なポイントが欠落している。
ほのめは怒りに肩を戦慄かせながら、神門を詰問した。
「アンタ……。私たちに〝死ね〟と言ってますの?」
「錆び付いた考えを捨てろ。データと成れば〝魂〟になど欠片も意味はない。時間の縛りからも解放される」
「知りませんわ! 独りでやってろ、ですの!」
「俺が自身の〝脳〟を直接いじるリスクは高い。AIのおまえたちに知識を叩き込み、俺の〝脳〟を託した方が成功率は格段に上がる。選択の余地は無い。理解はあとでしろ。なんなら世羅より先にほのめを優先しよう。世界で初めて、世界で一番の、生体AIの誕生だ。誇らしいだろう?」
焦点が定まらない、目的しか視えていない者の双眸。
蝶ヶ崎財閥が凋落していく最中で、幾度となく目にしてきた下衆な連中のソレと同じ。かつては目標とし、どこか憧れさえしていた人物は、底辺レベルにまで落ちぶれてしまっていた。
ほのめは〝魂〟の叫びを手のひらに込め、我欲に満ちた高弁を垂れ流す外道へぶつけた。
夕闇のカフェが騒然となる。
「……おぞましい。世羅と私に近付かないで頂戴」
彼にとって、共感は得られずとも、見下されるのは初めての経験。
頬の痛みを感じながら、神門は最適の言葉を模索し、音にした。
「願いを乞う立場の態度じゃなかったな……。悪かった」
「それ以前の問題ですの」
誠意の無さはすぐに見抜かれた。
「……聞いてもいいかな」
震える手でティーカップを握り締めた世羅が、視線を落としたまま、神門へ問い掛ける。
「私、春日ちゃんの生贄になるの……?」
「そうじゃない。世羅だって俺にとって大切な――」
「もう分かった。言わなくていいよ。聞きたくないから」
諭すように神門が発した音だけは、以前と変わらない。妹を気遣う兄のもの。
懐かしい想い出を穢され、顔を上げた世羅の瞳には涙が浮かんでいた。
「世界でたったひとり、大嫌いな子がいるんだ」
「そうか。おまえも辛い思いをしたんだな」
「私の想いはいつもその子に邪魔される。大好きな人はちっとも私を見てくれない。……ねえ。いま、みかにいは誰と喋ってるの?」
「なんの話だ?」
「私の面影に重ねてる、その子と、じゃない?」
「…………ッ!!」
核心を突かれて言葉を失った神門に、ほのめは呆れ返った。
「気付いてないフリかと思ってましたわ。本気で気付いてなかったなんて。最低最悪の屑野郎ですの」
「だって、おまえは、俺の妹、のような……」
「妹じゃないから、道具扱いするの? 生きてるんだよ? 考えて感じる〝魂〟があるんだよ? 春日ちゃんはとっくにいなくなったのに! 一生掛けたって、私に勝ち目なんかないじゃん!!」
世羅の訴えに、ほのめに叩かれた頬が、再びうずいた。
「……言い訳はしない。浅慮と無知を認めよう。そのうえで恥を忍んで頼む。助けてくれ、世羅、ほのめ。俺には敵が多過ぎる。俺の〝脳〟を託せる宛はほかに無い。おまえたちじゃなければ駄目なんだ!」
「無理だよ……。なんで分かってくれないの。……みかにいの馬鹿!!」
「世羅!!」
涙を疾走らせ、世羅は足早に立ち去った。
呆然とする神門を残し、ほのめもきびすを返す。テーブルにクレジットカードを投げ付けながら。
「お勘定。世羅の分も置いていきますの。お釣りは差し上げますわ」
「ほのめも俺を見捨てるのか?」
「ええ。〝脳〟はもちろん手も貸せませんの。……もし私たち三人がAIになったと仮定しても、問題は山積み。例えば全人類の記憶、具体的にどうやって手に入れる算段か教えてくれます?」
「一度は拘束する必要があるだろう。ただひとりの例外も無く」
「反抗勢力との衝突が発生しますの」
「尽く制圧する。各国の中枢にハッキングして武力を奪えば容易い」
「たくさんの血が流れますわ」
「案ずるな。落命したヤツからもデータは採集出来る」
「正気を疑います」
「俺は正気だ」
「アンタは妹に固執するあまり、あまりにも他者の尊厳を軽んじていますの」
「俺が手を下さずとも、遅かれ早かれ時は訪れるだろう。このまま機械科学が発達すれば個人情報は必ず管理されるようになる。わずかに未来を先取りするだけの話だ」
「仮にそんな哀しい結末が待ち構えているとしても――」
脱いだ白衣を小脇に抱え、背中越しにほのめは続ける。
いつしか、かんしゃくを起こした子供をあやすような、優しい口調となっていた。
「未来は未来。現在は現在。いまの倫理観じゃ、人道から外れた罪ですのよ?」
「時代の流れとともに禁忌は常識となる。歴史が証明している」
「詭弁ですわ。いずれにせよ悪事の片棒を担がされるなんて御免被りますの」
「人間が進化する瞬間に立ち会えるんだぞ?」
「興味ありません」
「冷静になれ」
「冷静になるのはアンタですの」
「すぐに返事を寄越せとは言わん。結論を急ぐな」
「熟考するまでもありませんわ」
「日を改めよう」
「二度と会いませんの。馬鹿とは」
「待て! 話は終わっていない!! おまえたちまで、俺を置いていかないでくれ!!!!」
追いすがる神門の手を、ほのめは振り払った。
「アンタは遥か先へ行ってしまいましたわ。ずっと追い続けていた背中は、もう、どこにも見当たりませんの」
黒崎研究室に対抗心を燃やし、蝶ヶ崎研究室を立ち上げた。
九頭竜学院大学の大学院時代。世羅が殴り込んで来たのは十年前にもなる。実家の手伝いで空けがちだった研究室は、いつしか世羅が連れ込んだ機械工学科の友人たちとの溜まり場へと変貌。少ない自由時間を幻獣の創造に費やそうとすれば、騒々しい世羅たちばかりか、気分転換と称した神門に邪魔されもした。
苦難の記憶がキラキラと光り輝く。
「馬鹿、か……。言う通りだな……」
崩折れた神門がかすれるような声で、悔恨の言葉を紡いでいる。
「なにが〝いままで通りで構わん〟だ……。なにが〝関係性が変わるわけでもあるまい〟だ……。なにもかも壊してしまったのか……。この、俺が…………」
冷たい秋風が通り抜けてゆく。
呪詛のような呟きが雑踏に紛れてしまっても、ほのめが振り返ることはなかった。
02 side. SERA and NANAO
神門の前から逃げるように走り去った世羅を、両手を広げて出迎える者がいた。
周囲のざわめきも気にせず、大声で泣きじゃくる彼女を包み込む。
ひとしきり感情をぶちまけた世羅が落ち着きを取り戻したのを見計らい、獅子島・レーベ・七尾は傷心の後輩へ優しく声を掛けた。
「よく頑張りましたね」
「……うん」
「よく気持ちを伝えましたね」
「うん……」
「つらかったですね、セーラ」
「うんっ!!」
七尾は蝶ヶ崎財閥の自社ビル、ミスティカルサイトのエンジニアとして働きつつ、護衛の役目も担う。
世羅が【機構破壊】を行使する様子が動画で拡散され、不特定多数から怨恨や好奇の視線を向けられるようになったためだ。
自慢のAIを搭載した小型ロボット〝ディア〟が、世羅の周囲を24時間監視している。
「シシシシマくらいのむねにくがあれば、みかにいも私を恋愛対象として見てくれたのかな……」
「恐らく関係ないですね」
「……振られたのが悔しいから言ってみただけ。十年前と変わってなかったもん。なんにも」
十年前――
「みかにいが、なんか、おかしい」
「黒崎博士が異常なのはいつもだろ」
「言えてる。彼は胸の大きなお姉さんに見向きもしないしね!」
「そんな話してない……」
雷鳥超と戦斗怜亜が、不満げに机へ突っ伏す世羅に〝いつも通り〟の反応を返す。
蝶ヶ崎研究室の丸テーブルを囲み、四人の若者が雑談に興じていた。
世羅と神門の馴れ初めは、彼らの九頭竜学院大学時代から、さらに十年遡る。
妹が急逝した報せを受け、母方の実家から生まれ育った東京へ戻った神門は、喪失感に苛まれる日々を過ごした。葬儀を終えたある日のこと、彼は妹と瓜二つの少女と運命的な邂逅を果たす。
しばし交流したのち、神門は九州へ戻ったが、互いの存在は互いの記憶へ鮮烈に刻まれた。
世羅は中学校の卒業直後、最難関と誉れ高い九頭竜学院大学に挑んだ。
流石に一年間の浪人生活を経験させられたが、翌年には見事に入学を果たしている。遺伝子工学の権威となった神門の研究を手伝いたいという熱意が、勉強嫌いの世羅にそうさせた。
「……レイア! さっきのはセクハラ発言ですよ? いちいち指摘するのも疲れましたが、ワタシにもいやらしい視線ばかり。親しき仲にも礼儀ありデース!」
「いやあ。子供の頃のクセが抜けなくてね。それはそれとして、黒崎さんの感性がズレてるのは確かだ」
「なんでみかにいの悪口言うの!?」
「おまえが真っ先に言い出したんだろうが……」
大学での世羅は友人に恵まれた。
20歳を迎えたばかりの怜亜は二回生。21歳の超と19歳の世羅は三回生。23歳の七尾は卒業を間近に控える四回生となっていた。夢を共有する怜亜と超、色欲に正直な怜亜と七尾、幼馴染の怜亜と世羅。年次こそバラけているが、活発で嫌味の無い青年を主軸に、奇妙な交流が始まるのは必然だったのかもしれない。
三年間はなんら接点の無かった世羅と七尾も、すぐに打ち解けた。
異能についても親身になって調べてくれたが、それについては、未解明のまま断念している。
「……ハァ。ワタシはなにもかも中途半端」
「急にどしたの、シシシシマ?」
「独り言。なんでもないデース」
機械工学科と電子工学科の双方に在席する七尾は、AI開発のエキスパートとして将来を嘱望された。……にも関わらず、分野がまったく異なる母の仕事を継ぐかどうかで心中は揺れている。
特殊な生い立ちから秘密主義な部分があり、仲間にも悩みを打ち明けられていない。
「……で? 黒崎博士がどうした?」
自動操縦の車椅子を走らせ、超が戸棚から回収したカステラを無愛想に投げ付ける。
言葉遣いはぶっきらぼうでも、面倒見の良さは抜群なのである。ちなみに、カステラは一瞬で消えた。
「どんどんやつれてる気がする。そもそも遺伝子工学科棟に来ないんだよね。無機物と有機物を融合させて無機生物を創り出す私の研究も、みかにいの研究ありきだから、ちっとも進まなくなっちゃった。それはどうでもいいんだけど……」
「どうでもいいものか。才能を活用しろ。もっと強欲になれ」
「黒崎サンならよく見掛けます。言われてみれば目の下にクマがあったような?」
「あちこちの学科棟に顔を出してるらしいよ」
「それ、ほんと!?」
思わぬ情報に世羅が身を乗り出し、残りの三人がそろって肯首する。
「研究も放りだして、なにしてるんだろ……」
「どんな天才でも人間は人間。行き詰まることもある。アイディア探しってとこだろう」
「だからって複数分野の掛け持ちなんて、僕なら〝脳〟がパンクしちゃうよ。女の子のお誘いならいくらでも受けるけど。あー。あづみちゃんと交際出来ないかなー。獅子島さんの後輩だよね? 紹介してよ!」
「レイアにだけは、絶対、紹介しないデース」
「ああ……。近くて遠い電子工学科! 彼女は千年に一度生まれ落ちるかどうかの最高に僕好みのおっぱ――」
「笑顔で最低ムーブすんな。ボコすよ?」
「痛ッ!? 殴ってから言うなよ。卑怯だぞ、倉敷!」
「もう一発いっとく?」
「あ痛ァッ!? すんません! 勘弁して!」
逃げる怜亜を追い掛ける世羅。
ふたりは退室してしまった。
「……解散するか」
「デースねー……」
そして、一夜が明けた。
四人は再び集まっている。世羅が所属する蝶ヶ崎研究室へ。
家業で大忙しの室長、ほのめは今日も不在だった。
「みかにいを捕まえて、問い詰めた」
「相変わらず行動力の塊だな」
「お陰で僕の小学生時代は黒歴史まみれだよ。ふふふ……」
哀愁を背負わせる怜亜を尻目に、神門の言い分が世羅から伝えられた。
いわく――
クローンを創り出す方法には目処がついた。
肝心のクローンに宿らせる魂の確保が絶望的だと判明。
遺伝子工学で手に入れた知識を電子工学へ活かしたいと考えている。
魂に代わるものをゼロから創出する。最高峰の人工知能を。
「それ以上は教えてくんなかった。むかむか!」
「やめて……。僕のこめかみをグリグリしないで……」
一般女子から大人気のイケメンも、幼馴染の圧には手も足も出ない。
「だから黒崎サン、頻繁に電子工学科へ出入りしてるんですね。ワタシも何度か声を掛けられました」
「えー!? なんで昨日教えてくれなかったの!? 親友に対する裏切りだよ!!」
「言おうとしましたよ!? セーラとレイアが喧嘩を始めて、言う機会を逸したんデース!!」
「せんとくんのせいかーっ!!」
「冤罪だーっ!!」
懐疑的な視線はそのまま親友にも向けられた。
「……何度も声掛けられて、恋しちゃったりしてない?」
「ノンノン! ワタシには結婚相手を選ぶ権利なんてありません! 話題もAIに関することだけデース!」
「自由恋愛が禁止なんて、忍者の末裔も大変だな。掟だの風習だのと古臭い」
「アハハ……。まあ、仮に恋愛OKでも、パパという最難関があります」
「物理学者にして免許皆伝のアメリカン・ニンジャ。どこのどいつだ、カール・ワイバーン」
「パパの出身はまさにドイツデース! スグルも上手いこと言いますね!」
「俺がダジャレをかましたみたいに言うな!」
「……忍者」
世羅がぽつりと呟く。
三人は反射的に身構えた。とんでもない提案が飛び出してくると確信して。
「みかにいの部屋に忍び込もう! でもって、最近なにしてるのか調べよう!」
「普通に犯罪だが?」
「みかにいと私の関係なら許されるから! たぶん! だから、みんなも手伝って!」
「せいぜいバレないようにやるんだな。俺は正義に反する行いには加担しないぞ。無論、怜亜も貸さん」
「そうだね。友達として聞かなかったことにはするけどさ」
「……うう~。……シシシシマ~」
「うっ。潤んだ瞳でワタシを見ないでください……。分かった! 分かりましたから! とはいえ、万が一にも家名に泥は塗れません。黒崎ルームのアンロックまでですよ?」
丑三つ時。なにもかもが寝静まった頃に作戦は決行された。
暗がりの中、木々を伝って壁に取り付いた七尾が、鍵の掛けられた窓を難なく開ける。
窓枠から縄梯子を地上へ降ろすと、すぐ近くの植え込みから世羅が顔を出した。
「黒崎サンは仮眠中。監視カメラは十分間だけ機能停止させました。見回りの警備員さんが接近したらお知らせします。なるべく手短に!」
「ありがとう。行って来る!」
久し振りに訪れた神門の個室はひどく散らかっていた。何度も推論を重ねて断念したのだろうメモ書きが、紙くずとなって散乱している。携帯食の包装ゴミや脱ぎ捨てた服も。
いつも几帳面な神門からは想像も付かない惨状だった。
異様な部屋の片隅に、ぼんやり光る箱が静かな旋風音を放っている。
世羅の人生とは無縁の物体。モニターは消されているが、いわゆるパーソナルコンピュータ。規格外の大きさであることから、かなりのハイスペックであると想像が付く。
「あれだけは触らないように注意して、と……。紙くずとかにヒントはないかな……?」
「何者だ!!」
「わわ!?」
唐突に部屋のドアが開け放たれた。
中腰になっていた世羅がバランスを崩し、後ろにひっくり返る。
「なんだ、世羅か。悪戯も大概にしろ。仮にも男の部屋だぞ? しかも、深夜になにをしてるん――」
神門の言葉が途切れ、表情が凍りつく。
世羅の指先が床置きのコンピュータに、ほんのわずか、触れていた。
「手を離せ!!」
直後に響き渡る爆発音。
「あっ! こ、壊しちゃった、かも……」
「どけっ! ああっ。……【春日】! 【春日】【春日】【春日】【春日】【春日】ーーーーッ!!」
世羅を払い除け、神門は煙を吹く本体に構わず、モニターをオンにする。
キーボードに指を疾走らせるが、吐き出されるのはエラー音のみ。
逡巡ののち、再起動も試みたが、無駄に終わった。
異変に気付いた七尾が死角から覗き見た光景は、尻餅をつく世羅と、愕然となり立ち尽くす神門。
「えっと……。あの……。いちおう……。悪気は無かったよ……?」
「……おまえ。自分がなにをしでかしたか分かってるのか? ……殺したんだ。人を。俺の妹を。【春日】を! 遺伝子工学に見切りを付け、独学で電子工学を学び、ようやく完成に近付いていた【春日】の人工知能を!」
「ご、ごめん。ごめんなさい、みかにい……」
「妹を差し置いて自分ばかり成長しておきながら、なにが〝みかにい〟だ。馴れ馴れしく呼ぶな!」
かつて無い凄まじい憎悪が、好意を寄せる相手から突き付けられた。
ずっと大切にして来た関係が、呆気なく壊れた瞬間だった。
激昂する神門は窓の外へ視線を移す。
「そこにいるのは獅子島か? ……ああ。繋がったよ。おまえたちは友人だったな。世羅をそそのかしたのか。どうせ俺に人工知能の権威を奪われるのが怖かったんだろう!!」
「ご、誤解! ……でもないんでしょうね。あながち……」
「シシシシマは悪くない! 私が巻き込んだだけだから!」
「結果がすべて。同罪だ」
「みかにい!」
「黙れ! 近付くな! その名で呼ぶなと言っている! ……顔も見たくない。二度と姿を現すな。報いを受ける日を、ただただ覚悟しておけ」
「ごめんなさい! ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい、ごめん、なさい、みか、にい……」
「……ソーリィ。行きましょう、セーラ」
うわ言のように謝罪の言葉を繰り返すばかりの世羅に肩を貸し、七尾は窓から飛び降りた。
眠れぬ夜が明け――
正気に返った世羅は泣きじゃくり、今度はひたすら七尾へ謝罪の言葉を繰り返している。神門は九頭竜学院大学および大学院で最高に近い発言力を有していた。叡智ある言葉に真っ向から刃向かえる者など皆無。
強制退学を覚悟していたふたりの元へ、想定外の人物が訪問する。
「みかに―― く、黒崎、さん……?」
「昨晩は言い過ぎた。謝る。この通りだ」
目を疑った。
完全なる被害者である神門が畏まり、加害者のふたりへ頭を垂れているのだ。
「顔を上げてください! ワタシたちこそあまりに軽率でした。言い逃れはしません。どんな処分も受け入れる覚悟です」
「では、折衷案だ。水に流そう」
「……え?」
「なんで!? だって、私、とんでもないことしたんだよ!? 人を……。あなたの妹を、こ、殺――」
「違う。壊しただけだ。あれは到底〝俺の妹〟とは呼べない代物だった。バックアップも取ってないような未完成品。むしろ方針を改める機会となった。感謝さえしている」
「許して、くれるの……?」
理解が追い付かない。
かろうじて、かすれそうな声が絞り出された。
「許すか許さないかを問われれば〝許す〟が、距離は置かせてくれ」
「……そっか。そうだよね。うん」
「俺はこれから本格的に電子工学の道へ進む。完璧な【春日】を生み出すためにな。少なくともこれまで以上に電子機器を扱うこととなる。世羅を関わらせるわけにはいかない。……仮に二度目が起きたとして、冷静さを取り戻せる自信が無いんだ。納得してくれ」
「ううん。私こそ、いつまでも子供のままで迷惑掛けた。本当にごめんなさい」
幾度目とも知れない謝罪に返答は無かった。
もはや神門は世羅を見ていない。
「獅子島」
「はい」
「おまえには引き続きアドバイスを願いたい。人工知能分野において、少なくとも現在の頂点は、おまえを置いてほかに無い。卒業までの半年足らずだが、頼めるか?」
「分かりました。ワタシの知識をすべて託しましょう。必要があればいつでも連絡してください」
「助かる。あとは各務原との繋がりも必要だ。パイプ役を果たしてくれるか?」
「電子工学科の一回生で頭角を表し始めたばかりなのに、よくご存知ですね」
「当然だ。九頭竜学院大学関係者すべての能力を把握しているからな」
親友は乞われ、自分は拒まれた。
許されたのは七尾の知識と人脈。おまけのおまけに過ぎないのだと悟り――
午後の雑談タイム、世羅は精彩を欠いた気色で仲間に伝えた。
「せんとくん、ちょーくん、お願い。みかにいが困ってたら助けてあげて」
「ん? べつにいいけど? あの人に頼られることなんてあるかな?」
「……なにがあったか知らんが、まあいい。心に留めておく。だが、おまえらも俺らを頼れ。いいな?」
「うん。ありがとう」
「サンクス、です」
神門は遺伝子工学科から電子工学科へ移籍し、世羅は自身の研究を打ち切った。
七尾が大学を卒業し、いつしか怜亜や超とも疎遠となる。
四回生の間は寮に引き籠もった。黒崎博士の邪魔をした厄介者として後ろ指を刺された。
誰もなにも言わない。聞かない。打ち明けるのを待っているのかもしれない。
無為な毎日が過ぎてゆく。
なんの成果も残せず、大学から籍を外す手続きをしたあと。
見兼ねたほのめに拾われ、七尾とも再会し、いまに至る。ふたりの慈悲が壊れ掛けの世羅を支えた。
「なんで私だけが、こんな要らない能力、持ってるんだろう……」
それは、遠い遠い宇宙の果てからやって来た、クスミカモのギフト。人智を超えた異能。
子供にとっては楽しい必殺技も、大人になって以降は、いつも足を引っ張る。
クスミカモにとって最初の友達である〝世羅本人が望んだ超能力〟という真実はとっくに忘れた。否。虚数領域と化した第6星界において、その果てにある事物は認識不能。ゆえに記憶は完全に失われている。
あの日以来、神門は世羅に連絡を寄越していない。
ついさっき呼び出されたのも、ほのめ経由で声を掛けられただけ。
神門は明確に世羅を避けている。理由は歴然。どうしても手の届かない妹を想起させるからだ。
「それでも! 覚えててくれたのが嬉しかった! ……なのにっ!!」
いま、してあげられるのは、小さな背中をさすることだけ。
泣いてばかりの親友に、プライベートの時間を割けないのが、なんとも歯がゆい。
七尾はデネボラを名乗り、アルタイルこと怜亜や、カノープスこと超とともに、シャスター開発計画へ携わっている。人類の明るい未来へ繋がると信じて――
計画は水面下で進められている。誰にも明かせない極秘プロジェクト。
シャスターの根幹となるAIに親友の〝脳〟が使われようとしていること。計画の首魁たるソルが神門であること。これらの最高機密は、当事者である七尾さえも知らされていなかった。
報いを受ける日が、迫る。
03 side. MIKADO
成果物を世羅に壊されたあの日。
妹を完全再現した人工知能は、正攻法で創れるものではないと悟る。
神門は似たような苦悩を抱える人物を知っていた。
彼女の娘である【あづみ】が九頭竜学院大学の一回生として、電子工学科へ在席していることも。
七尾を介して【あづみ】と接触し、彼女を〝創った〟生みの親とのパイプを手に入れた。
だが、情報交換もそこそこに各務原博士は死去。
途方に暮れる神門に接触を謀る者がいた。
「落ち込んでるようだね。ボクが力を貸してあげよう」
「……誰だ」
「ユーと呼んでくれて構わない。英語の二人称〝おまえ〟だ。他人に興味の薄いキミにはうってつけだろ?」
「からかいにきたのか?」
「とんでもない。アドバイスとサジェストだよ」
得体の知れない異邦人は流暢に神門を煽る。
「君に足りないのは覚悟だ」
「貴様に言われる筋合いはない。研究に生涯を捧げる覚悟なら、とうの昔に出来ている」
「キミのことはよ~~~~く知ってるよ。理由は秘密だ。いまはまだ〝セーカイカンキョーテー〟をおおっぴらに違反出来ないからね」
ユーはオーバーリアクションで肩をすくめてみせた。
「胡散臭い男め。ならば問おう。俺に覚悟が足りないとする論拠を示せ」
「簡単な話だよ。キミは自分しか犠牲にしないじゃないか。他人を踏み台にすればもっと高みへ到れるのに、ああもったいない! 革命を成し遂げるには犠牲がつきものだというのに!」
「……笑わせるな。犠牲の果てに復活を遂げたとしても、妹は喜ばん」
「これは失礼。お優しいキミに〝犠牲〟という言葉は刺激的だったかな。ならば言い換えよう。〝手伝って〟もらうのさ。キミにだって心を許せる友人のひとりやふたりいるだろ?」
咄嗟に浮かんだのは世羅とほのめの顔。
PC爆破事故の後日、監督不行き届きを理由にほのめからも謝罪があった。やはり〝水に流す〟と伝えたが、以来は互いに距離を置いている。頭ごなしに叱り付けてしまった世羅には、特に会わせる顔がない。
縁は切れたも同然だった。
「……いないな」
「随分と寂しい人生じゃないか! だったらボクがひとり紹介してあげよう。……聞いてたかい? 黒崎博士の承諾は取り付けたよ」
『よく言うわ』
ユーはいつの間にか取り出した携帯端末で、誰かと通話を始めていた。
外部スピーカーから相手の声が聞こえてくる。
『貴方が黒崎神門かしら。うわさは兼ね兼ね。私はクロエ。人間に絶望した科学者よ』
「……なんのつもりだ。俺は貴様らに用など無いが」
「人の話は聞くものだよ。続きを、クロエ」
『人間は利己的で醜い。だから、私は機械に管理させるべきと考えているわ。平等にね』
「ボクも人間はいずれ自滅すると憂いているよ。だから、人工知能による管理が最適解だと考えてる」
「随分とエキセントリックじゃないか」
ふたりの言い分はテロ組織の一員のように極端なものだった。
「貴様らの持論を頭ごなしに否定はしない。俺も決して人格者ではないからな」
『けれど、目的は一致している。人間を超越する優秀な人工知能の創造よ』
「最終形態がキミの妹ベースだろうと、ボクらは構いやしない」
「勘違いするな。俺は優秀な人工知能など求めていない。必要なのは平凡で完璧な――」
「完璧な平凡さを再現するにも優秀なスペックが求められるわ。独力で創れるの?」
「…………」
奇しくも挫折を味わった直後。
神門は言い返せる言葉を持たなかった。
「途中でプロジェクトを抜けてくれてもいい。だとしても、その瞬間までは良好な協力関係を築けそうだと思わないかい?」
「……癪に障るがいいだろう。せいぜい俺を利用しろ」
「おおっ。交渉成立だ。嬉しいよ!」
『以降はオンラインでのやり取りを提案するわ。私はポラリス。口調も変えるからそのつもりで』
「ポラリスというと、夜空の定位置で輝いてる北極星かい? 姿や立場を変えながら裏社会で暗躍してきたキミにしては、皮肉の利いた名前じゃないか。だったらボクも星になぞらえ、アルクトゥルスを名乗ろう」
「俺はソル。人工知能はルナ。構わんな?」
『どうぞ。次はネットの海で』
それから――
各務原博士の忘れ形見【あづみ】に声を掛けた。知能レベルは高く、唯一無二の特別な生い立ちもある。生きる目的を見失っていた彼女は誘いに乗り、オンラインではベガを名乗った。
しばらく時間を置き、手筈通りにポラリスとアルクトゥルスも合流。彼らはアメリカの大企業ハイドラ財団をスポンサーに引っ提げ、スーパーコンピュータ【NIS】の管理者権限をも掌握していた。バージョンアップの暁には【シャスター】への改名も決定。順調な滑り出し。
……などということはなく。
ソフトウェア方面、つまり、人工知能の進捗が芳しくない。
「やはり獅子島のセンスが必要か……。だが、首を縦に振らん。いつぞやは〝必要があればいつでも連絡してください〟などと調子の良いことをほざいていたのだがな」
『ボクもスカウトを試みたけど、ダメだったよ。家業を継ぐのってそんなに大事かい? ただ、心は揺れてるように感じたね。あとひと押しで落とせると思うんだけど」
『獅子島先輩かあ……。それなら! わたしにアイディアがあるよ!』
明るい声で発言したのは、普段はあまり自己主張を行わないベガだった。
はしゃぎ過ぎたと気付き、恥ずかしそうに言い直す。
『……えっと。わたしにアイディアがあるよ。戦斗先輩を誘うのはどうだろう』
『なんじゃ、そやつは?』
「大学関係者だ。だが、あいつの分野は機械工学。ハードウェア方面なら貢献してくれるかもしれんが」
『彼を仲間に引き入れれば、親友の雷鳥先輩もセットでついてくるはず。そうなれば――』
「同じことだ。ロボットだのパワードスーツの開発に傾倒する熱血馬鹿に用は無い」
『熱血馬鹿とな。妾と相容れることは無さそうじゃのう。却下じゃ』
『そんな~~~~』
『……いや。悪くない案だよ。流石はベガ。ボクたちには決して思い付かない感情任せの発想だ!』
「そ、そう? えへへ。照れちゃう」
同志となった直後は暗く沈んでいたが、ベガは徐々に心を開いていった。
もとい、開き過ぎだった。いまやプロジェクトメンバーでもすっかり浮いた存在と化している。
そのような日々の変化を考慮してもなお、今日の彼女は特別に様子がおかしい。少なくとも昨日までの彼女には、引っ込み思案で遠慮がちな小動物要素が前面に出ていた。
「俺にも分かるよう説明してくれ、アルクトゥルス」
『彼らには懇意にしている人間が三人いるだろう? 倉敷世羅と蝶ヶ崎ほのめの頭脳も並外れているが、遺伝子工学に偏った知識は不要。はてさて。残るひとりは誰だったかな?』
「人の心を動かすのは、人の心というわけか。そう上手くいくものか?」
『あとはわたしに任せて!』
「待て、早まるな。確実な計画を模索――」
神門の制止など耳に入らない。
憧れの先輩との接点を得るため、ベガは凄まじい行動力を見せた。
『返信来た! えっとね。〝あづみちゃんのお誘いなら喜んで手伝うよ。どんな計画か知らないけど!〟だって! きゃ~! きゃ~!』
『軽薄そうな男じゃのう。仲間に引き入れて良いのか?』
「正義のプロジェクトだとでも伝えれば問題ないさ。相棒クンにもね」
『アルタイルを名乗って欲しいってお願いしたら、そっちもOKだって! やった~! やった~!』
「本題を忘れるな……。責任を持って、獅子島を引きずり出せよ?」
悲嘆の底から一周回り、ベガは恋する乙女と化していた。
子孫を残せないクローンであることを絶望したりもしたが、いまや、いざとなったら創り出せばいいとさえ割り切っている。愛があれば大抵の障害など些事に過ぎないとも。
もはや忠告は無駄と察し、神門が最低限の釘を刺す。
「くれぐれも戦斗、雷鳥、獅子島の三人に俺の本名を明かすなよ? その一線を超えるようなら提案は無効だ。おまえもプロジェクトから除名させてもらう」
『うん。分かったよ。信頼関係は大事だもん。先輩との共同作業が叶うなら、迷惑は掛けない』
願望は原動力となる。
それは誰よりも神門が識る事実だった。
『でもね、理由は先輩だけじゃない。わたしに居場所をくれて感謝してるから、お返ししたかったんだ。ホントはポラリスさんとアルクトゥルスさんが最初期メンバーなこととか、すべてを記録するスーパーコンピュータを完成させた先に次の目的があることも、なんとなく知ってるよ。……でも、わたしからは聞かない』
「……気付いていたのか」
『あはは……。いつもお母さんの機嫌を伺ってたから、感情変化には鋭いかも? 隠し事は不可能と知れ~!』
プロジェクトのオマケメンバーと捉えていたベガの意外な洞察力に、神門は驚きを隠せなかった。
得手不得手は誰にでもある。
だとしても、相対的に自分自身が他者の心の機微に鈍くなっている事実を思い知った。研究に没頭していたせいか。それとも――
『いろいろ教えてもらえないのは寂しいけど……。いつか本当の仲間にしてくれる日を楽しみにしてるね』
「貴様は本当にベガか? 別人じゃないのか?」
『そう言われても……。だったら、いまからわたしは〝新生ベガ〟!!』
『意中の男が加わるくらいでこうも変わるか。だから人間は信用ならんのじゃ』
『え~。ひどいよ、ポラリスさん!』
数日後――
ベガの口利きが功を奏し、アルタイル、カノープス、デネボラが加わった。
かくして、七人のプロジェクトメンバーはシャスターのアドミニストレータ(管理者)となる。
以降、ハードウェア方面の調整はアルタイルとカノープスに一任。ソフトウェア方面はデネボラが開発リーダーに任命され、四人の天才が試行錯誤を重ねる。
計画は極めて円滑だった。……とは、やはりならない。
飛躍的に進化したシャスターの人工知能に、自らの将来を演算させた結果は、無情なものだった。
神門が望むような、人間同等の人格を人工知能が備えるまで、あと百年。
進化の着地点に固有の人格を加味するならば、さらなる年月が必要と算出された。存命のうちに春日との再会は叶わない。
ほかのメンバーは人工知能に【春日】を求めているわけではない。知る由も無いが、ポラリスとアルクトゥルスは時間的な制約にも縛られていない。ベガ、アルタイル、カノープス、デネボラは志を引き継ぐ次世代が成就すれば良しとの見解を示した。
神門のみ、モチベーションをダウンさせている。
「……なんの用だ。リアルでの会合は禁止のルールだが?」
「固いこと言うなよ。どうせ放っておいてもキミは立ち上がるだろうけど、ボクはおせっかいなんだ。寿命を迎えるのが怖いなら、ボクらが創ったシャスターに解決策を問えばいい。……人類が滅ばない方法をね」
悪魔のささやきによって、神門は最適解を得た。
人間の記憶と生体情報を得るだけに留めず、データ化するという、悪魔の所業を――
自身の〝脳〟を人工知能化、前段階で他者の〝脳〟を人工知能化するという、悪魔の発想を――
悪魔と化した天才による、悪夢が幕を開けた。
無人戦闘機が人間を襲う事件が多発。襲われた者は決まって神隠しとなった。
アドミニストレータの誰もがシャスターの暴走によるものだと直感した。ポラリスやデネボラが調査するも、原因は特定されず。なんのことはない。最高権限者である神門の意思によるものだからである。
シャスターの存在をまだ知らない世間は、陰謀論と世界大戦の始まりを吹聴した。
ひとり。またひとり。犠牲を代償に〝脳〟の人工知能化技術が確立されてゆく。
身内さえも例外ではなかった。
『どうして!? わたし、信じてたのに……。みんなのこと!!』
「俺の独断だ。俺はおまえが恐ろしい。信じてくれるおまえを、俺は信じてやれそうにない」
実験過程でベガの記憶と感情が殺された。
明るく真っ直ぐな性格は、いつか真実を知った日、邪魔になると感じた。
恋愛は人心を容易く変えてしまう。アルタイルに対する想いも捻じ曲げた。
ゼロからイチを創出するのは困難でも、イチやヒャクは容易くゼロとなる。
『人間はことごとく管理されるべきです……』
「証明完了。記憶と感情の調整に狂いは無い。礎となってくれて感謝する」
シャスターの制御不能やベガの変貌は、遅れてプロジェクトに加入した三人の態度を硬化させた。
顕著だったのがカノープス。シャスターの破壊を宣言するだけには留まらない。
『ソル、俺はおまえを糾弾する。ベガへの冒涜も、各地の行方不明事件も、無関係とは言わせない。……なによりもだ。プロジェクトの最終目標が妹の復活だと? ふざけるな! 亡くなった人間のために生きている人間を犠牲にするなど、許されてたまるか!!』
「カノープス、何故、貴様が……!」
よりにもよって最重要の機密情報を把握されていた。
アルクトゥルスとポラリスしか知らない真実。どちらかが裏切った裏付け。どちらも疑わしい。
「残念だが、俺たちのプロジェクトは終わりだ。俺の計画へ移行する」
『待て! 話は終わっていない! ……クソッ。必ず追い詰めてやるからな!!』
躓いている場合ではない。
迷いが無いと言えば嘘になるが、決断の時は来た。大義のために受け入れてもらう。
神門は数年来となる友人へ連絡を試みた。
最初に世羅の電話番号を入力し、首を振る。オリジナルの人工知能を破壊された直後の気まずさが忘れられない。結局、まずはほのめにメールを送り、世羅にも伝えてもらう形を取った。
もはや誰も頼れないが、あのふたりだけは特別。きっと理解を得られると確信し――
提案は拒まれた。
縁を切られた。
呆気ない最後。
希望は失われた。
人間の“魂”を失くしていると、想い識らされた。
「何故もっと早くに気付かなかったんだろうな。手っ取り早い解決策があったじゃないか。なにもかも失ってから気付いたよ。……俺が春日のところへ行けばいいんだ」
九頭竜学園大学で最も優遇されている黒崎研究室を擁する棟は、ものものしい雰囲気に包まれていた。
強権をもって人払いを済ませた神門は、研究成果もろとも、爆破による自害を宣告した。機械科学が発達しようとする世で、敢えて原始的な死を選んだのである。
予定時刻きっかり、計画は断行され――
現在、神門は生きている。
「どうだい? よく撮れているだろう、ソル」
「伝えなくていい……。知りたくもない……」
「かくも非道いラストを招いたのは、キミ自身の愚かな選択のせいだよ、ソル」
動画にふたりの人物が映っていた。
黒崎研究室を目指してひた疾走るのは、世羅とほのめ。
最初の爆発。
建物が倒壊を始める軋み音が動画に混じり始める。
世羅が電子ロックを破壊した。スプリンクラーの水を浴びたふたりは灼熱の業火を迷わず駆ける。
ほのめが触れた壁は何故だか崩れた。砂状になった壁はすぐさま熱で溶け、焦げ跡を残して蒸発。途中経過の黒い液体は、こんな時にも関わらず、妹が好きだったカスタードプリンのカラメルを想起させた。
「珍しいだろう。彼女も異能持ちだ。思わぬところで第7星界を強請るネタができたよ」
「……星界?」
「いよいよハイライトだ。キミのために決死の覚悟で駆け付けてくれた、ふたりのフィナーレだよ!」
「やめてくれやめてくれやめてくれ、頼む、やめてくれ……」
「キミには知る権利がある! 義務がある! 目を! 耳を! 最大限に研ぎ澄ませて感じるといい!!」
二度目の爆発。
一瞬、ふたりと目が合ったのを思い出した。
どうしてか。ふたりは〝してやったり〟とでも言いたげな笑みを浮かべ――
「やめろおおおおおおおおおお!! 来るな世羅!! 進むなほのめ!!」
世羅に蹴り飛ばされたほのめが、神門を包みこんだ直後、灼炎が画面を覆う。
映像は途切れた。
「なんで、どうしようもない俺なんかを、救ったんだ……」
世羅は圧死、ほのめは焼死、だったという。
爆発を逃れられなかったながらも、神門は生かされた。
妹に続き、またしても最期の言葉を聞いていない。
「キミのピンチと聞いて、ボクも駆け付けたんだよ? 万雷の拍手喝采と感謝の美辞麗句を送って欲しいものだね。大事な大事なキミの友人ふたりを、比較的無事な状態で回収出来たんだから。首から上だけ、ね。つまり〝脳〟は無事だ。必要だったんだろう、コ・レ・が……!!」
「貴様ああああ!! ユークトゥルス!!!!」
「おやおや。本名を突き止めていたとは驚きだ。流石はボクが惚れ込んだ人間だよ。だけど、感情に流されるようじゃ、まだまだだ。……オイ。いま誰に向かって暴言を吐いた? 冷静になれよ! オラッ! 調子こいてんじゃねえぞッ!!」
殴り返したくとも、身体がまったく動かない。
生きているのが奇跡と言われるほどの外傷を負ったのだから当然だった。
容赦無く振り下ろされ続ける拳に抗えず、だんだんと意識が沈みゆく。
「ハハッ。やり過ぎたかな! せっかく〝脳〟を人工知能に落とし込む技術を確立出来たのに、残念だったね。死ねば楽になれるよ。キミに生きて欲しいと願った、ふたりの想いを踏みにじれるものならね……!!」
「き゛さ゛ま゛か゛! 世羅とほのめを! か゛た゛る゛な゛! ……うう。うあああ!!!!」
途切れ掛けた意識が引き戻された。
最後の理解者をふたり同時に喪った現実が、怒涛のように押し寄せて来る。
「いい大人が泣き叫んで、みっともない。頼むからボクの嗜虐心を刺激しないでおくれよ。数日、ゆっくり考えるといい。進むも止まるも戻るもキミ次第だ」
「……ま゛て゛」
立ち去ろうとするユークトゥルスを、神門が呼び止める。
涙と鼻水に塗れた顔のままだが、毅然とした表情を取り戻している。
「……ふたりを丁重に保管しろ。細心の留意を払え。損傷が及ばんようにな」
「いいね! 即断即決か! オーケーオーケー。それでこそだよ、ソル」
「回復までニヶ月の猶予を寄越せ。カノープス、アルタイル、デネボラを見張れ。ポラリスもだ」
「ボクひとりで四人を監視しろって? 無茶を言うなよ」
「奴らも迂闊には動けん。シャスターの脅威を知ったら世は混乱に陥るからな」
「へえ? 意外と冷静じゃないか。いいとも。任されよう」
「理解が早くて助かる。……失せろ」
神門は世羅とほのめの〝脳〟をデータ化した。
しかるのち、史上最高のデュアルコアは自身をデータ化させた。
「参ったね。いくらなんでも想定外だ。あの致命傷から二週間で動けるようになるかい? カノープスやアルタイルの牽制に掛かりっきりで、なにひとつ小細工してる間も無かったよ。ボクとしたことが!」
「だろうな。計算通りだ」
「頑張りに免じて教えてあげよう。裏切り者はポラリスだ。どういうわけか、心変わりしたみたいでね」
「だろうな。推測通りだ」
「素晴らしい。流石はソル!」
「貴様の顔は二度と見たくない。シャスターのミラーでも眺めてろ。……永遠にな」
誰もがこう考えた。黒崎神門は少なくともニ~三ヶ月動けない。
余裕を持って反撃準備を行う。余裕を持って策謀を巡らせる。天才に立ち向かうため万全を期す。
誰もが知らなかった。黒崎神門という人物は予想の範疇になど収まらない。
ソル以外のアドミニストレータは六人同時にデータ化された。不都合な記憶は上書きされた。将来的な反逆が想定されるカノープスには、ふたつめの人格が植え付けられた。
ソルの護衛には正義感の塊のような人物が据えられた。
シャスターが弾き出した最適解は、縁も縁も無い、都城出雲という剣術に長けた人物。哀れな男はデータ化される際に〝ソルが真実〟と刻み込まれた。
――真冬の深夜。
世界の何処かで彼が見上げる星々は【パピス】と呼ばれる星座を描いている。
「おまえたちの本心はもはや紐解けん。ならば、せめて俺が本心を語ろう。世羅、ほのめ……。少なくとも俺にとって、おまえたちは〝とも〟だった。振り返ればいつもいてくれた。当たり前に感じていた。……だが、お別れだ。もう〝俺を置いていかないでくれ〟なんて我儘は言わないよ」
神門は並んだ墓に、名も知らぬ二輪の花を供えた。
安価な駄菓子と最高級のカステラを添えて。
「いつでも全力でぶつかって来たよな。〝半端な好敵手〟ほのめ。データと化してもビンタの痛みは残っているぞ。……俺如きを本気で叱ってくれてありがとう」

Illust. ちゃきん
「それと世羅。慕ってくれる想いの変化に気付いてやれず、済まない。俺の思考は〝妹と同等〟で止まっていたようだ。……こんな俺を好いてくれてありがとう」
しばし黙祷し、顔を上げると――
星座の向こうに微笑むふたりが見えたような気がした。
思わず手を差し伸べてしまうが、都合の良い幻想だと気付き、引っ込める。
「俺たち三人の誤算は、黒崎神門という人間がとてつもない阿呆だったことに尽きる。……だが、敢えて愚直に進ませてもらおう。おまえたちにとっては不本意だろうが、知ったことか。俺は目的のためならば――」
「どんなことも厭わない」